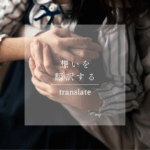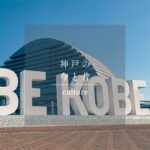前回の記事では「住民一人一人が物語を作る」とお伝えしました。今回の第3章では、物語に出てくる人々の感情から街を育むとどうなるのか、お話していきます。
3.愛される街に必要な「3つの感情設計」
(1) 安心感
──「ここなら暮らせる」と思えること
住民が街に感じる最も基本的な感情は、「安心感」です。犯罪が少ない、安全に歩ける歩道がある、災害時に避難できる体制が整っている。
そうした物理的な安全性に加え、「この街には知っている人がいる」「困ったときに声をかけられる人がいる」といった精神的なつながりも、安心感を生む大切な要素です。
安心感は、行政による防災や福祉の整備と、市民どうしのゆるやかな関係性の両方から生まれます。それは、街を「選ぶ」きっかけであり、「住み続けたい」と思える理由にもつながります。
街づくりにおける「安心感」の具体例
| カテゴリ | 行政 | 市民 |
|---|---|---|
| 整備 | 歩行者優先の道路整備(ゾーン30など) → スピード抑制や見通し改善により、子どもや高齢者が安心して歩ける環境に。 | 子どもが安全に通学できる「見守りボランティア」活動 → 地域の高齢者や保護者が通学路に立つことで、親世代の安心感が高まる。 |
| 子育て | 地域の見守りカメラの設置とプライバシー配慮 → 犯罪抑止と安全性の向上につながりつつ、市民の信頼関係も守る工夫が必要。 | 保育園や小学校との連携による地域ぐるみの子育て支援 → 「街全体が育てる」という感覚が、若い世代の安心感と信頼を生む。 |
| 災害 | 地域内の防災マップ配布と訓練の定期実施 → 危険箇所と避難場所を「知っている」ことで非常時にも落ち着いて行動できる。 | 災害時のペット同伴避難所の確保 → 大切な家族(ペット)を守れることで、本当の意味で「安心して避難」できる。 |
| 公共 | 公園や公共空間における照明設備の設置と維持 → 夜間の見通しがよく、女性や子どもも不安を感じにくい街に。 | 地域SNSや掲示板による情報共有・見守りネットワーク → 小さな変化や困りごとが共有されやすくなり、孤立や事故の予防につながる。 |
| 高齢者 | 高齢者向けの「おたがいさまサポート」制度 → 独居高齢者を地域全体で気にかける取り組みが、住民全体に優しさと安心をもたらす。 | 顔見知りが増える「町内会の季節イベント」 → ご近所同士が名前と顔を知っているだけで、心理的な安心が大きくなる。 |
(2) 誇り
──「この街に住んでいることが嬉しい」と思えること
人は、自分の所属する場所に誇りを感じるとき、その場所をより良くしたいという気持ちが自然に生まれます。
伝統的な祭りや景観、地元ならではの食文化など、外からも認められるような魅力を知ることは、住民にとって「自分の街を誇りに思う」体験につながります。
また、こうした誇りは一方的に与えられるものではなく、住民自身が主体的に関わり、学び、語ることで育っていきます。
街づくりにおける「誇り」の具体例
| 1 | 地域の伝統行事や祭りを次世代と継承する取り組み → 子どもたちが地元の歴史や伝統に触れ、語れるようになることが郷土への誇りにつながる。 |
| 2 | 市民が案内役を担う“まち歩きガイド”の仕組み → 外から来た人に街を語れること自体が誇りを育てる行為となる。 |
| 3 | 地元高校と連携したご当地グルメの開発やイベント開催 → 若い世代が「自分たちの街の味」を自ら発信する機会が、誇りと愛着の醸成につながる。 |
| 4 | 景観条例の制定と、住民参加による町並み保全活動 → 美しい景観を「守る主体」であるという意識が、誇りを生む。 |
| 5 | 歴史的建造物のリノベーションと市民公開 → 「この建物がある街に住んでいる」ことが誇らしくなる象徴的な資産の活用。 |
| 6 | 全国的な受賞歴(例:ガーデニング、教育、子育て環境など)を住民に共有 → 客観的な評価を住民自身が知ることで、誇りと自信につながる。 |
| 7 | 街のロゴやブランドメッセージを市民と共に考案 → 言葉にする過程で、自分たちの街の価値に気づくきっかけとなる。 |
| 8 | 小学生による「わたしのすきな〇〇市」作文コンクール → 子ども目線の街への愛情が共有され、大人も再認識する機会となる。 |
| 9 | 地元出身の人物(スポーツ選手、文化人)を街全体で応援する風土 → 「この街からこんな人が育った」という象徴が地域誇りの源になる。 |
| 10 | 空き家や遊休地を使った市民プロジェクトの実施 → 何もなかった場所に「自分たちの手で価値を生み出した」という実感が誇りとなる。 |
(3)共感
──「この街の想いに共鳴できる」と感じること
最後に重要なのが「共感」です。街の方針や取り組み、未来に向けたビジョンに対して、住民自身が「それなら私も関わってみたい」と思えるかどうか。これは一方通行の情報発信だけでは生まれません。
行政が、住民の声に耳を傾け、共に考え、共に形にしていくプロセスを重ねることで、住民の中に「この街と私はつながっている」という実感が育ちます。
共感は、人を街の傍観者から担い手へと変えていく力を持っています。
街づくりにおける「誇り」の具体例
| 1 | まちづくりワークショップや住民参加型会議の定期開催 → 意見を聞くだけでなく、実際に反映される体験が「自分ごと化」につながる。 |
| 2 | 市民提案型事業(例:市民からアイデアを募り予算化) → 街の未来を一緒にデザインしているという感覚が共感を生む。 |
| 3 | 「子育て世代の声を反映した公園整備」プロジェクト → 自分たちのライフステージが行政に理解されていると実感できる。 |
| 4 | 地域通貨やボランティアポイント制度の導入 → 街の活動に参加することが「楽しい」「得になる」という感情的共感を促進。 |
| 5 | 市民インタビューやローカルストーリーの発信(SNS・広報誌) → 他の市民の声に共感することで、「自分もこの街の一部」と感じられる。 |
| 6 | 移住者と地元住民の交流イベントの開催 → 新しい視点と地元の歴史が交差し、双方に共感が育つ。 |
| 7 | 障がいや多様性をテーマにした地域上映会・対話イベント → 「知らなかった」から「わかり合える」へと感情の橋をかける。 |
| 8 | 行政職員が直接現場に出向いて対話する「出張まちづくりカフェ」 → 形式ばらない対話が信頼と共感を醸成する。 |
| 9 | 住民が撮影した“わたしの好きな街角”フォトコンテスト → 街への視点を共有することで、他者の想いにも共感できるようになる。 |
| 10 | 地域未来ビジョンの策定に市民の文章・声を直接採用する → 行政の理念が「自分たちの言葉」で語られるとき、街への共感が深まる。 |
感情設計は「仕組み」ではなく「関係性」から生まれる
「安心感」「誇り」「共感」という3つの感情は、それぞれが単独で機能するものではありません。それらは街のあらゆる営みの中で交差し、共鳴しながら、じわじわと育成されていくものです。
感情設計とは、制度や施策だけで完結するものではなく、人と人、人と街との関係性の中から育まれていくものです。
これらの感情を育てる環境を丁寧につくっていくことこそが、街が「選ばれ、愛され、支えられる存在」として生き続けるための基盤になるのです。