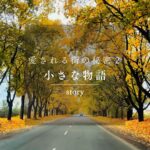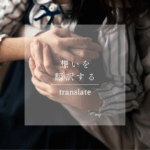「住みたい街」に必要な3つの感情設計
街を歩いていると、ふと賃貸物件の看板が目に入りました。
「住みたい街ランキング1位:〇〇市!」
そこには補足で「大型ショッピングモール」「学校・病院」「コンビニ・スーパー」が近くになって便利!と書いてありました。
でもそんなに便利な街は一部に集中していて、どこでもそのような街をつくれるわけではありません。
それでも住みたいと思える街とはどのような街なのでしょうか。
この記事では地域ブランディングに必要な3つの感情設計について3章にわけてご紹介します。
1. 「街づくりは行政の仕事」
その思い込みを住民と一緒に変えていく
1-1. 街づくりにおける住民と行政の役割の違い
冒頭でもお伝えした通り、私たちが住みたい街の条件に「利便性」が上位に上がってきます。ショッピングモールや学校、スーパーなどのインフラ関連は行政が関わっています。そのため気が付けば「街づくりは行政が担うもの」という考え方が住民の中でも根付いています。
確かに、インフラの整備や公共施設の設置、福祉サービスの提供など、行政が果たす役割は街の基盤を支える上で欠かせないものです。しかし、それは街の一部に過ぎません。
行政が整えるのは、いわば街の"骨格"です。そこに命を吹き込み、日々を色づけていくのは、暮らしを営む人びとの想いと営みです。自然を感じながら「おはよう」の声。商店街の小さなイベント。子供たちが安心して美味しそうに食べる姿…。そんな何気ない瞬間が、街に温もりを宿していきます。
つまり「住みたい街」は、行政と住民で一緒に育むことによって生まれるのです。
| 住みたい街とは | 行政の役割 | 住民の役割 |
|---|---|---|
| 目的 | 社会基盤・制度の整備 | 生活文化・地域アイデンティティの養成 |
| 手段 | インフラ整備、制度設計 | 日常的な交流、地域活動、文化の継承 |
| 成果 | 利便性の向上、安全性の確保 | 街への愛着、誇り、共感 |
行政の整備によって利便性や安全性が高まったとしても、そこに暮らす人びとの想いが重なり合わなければ、街はただの構造物に過ぎません。街を本当に育てていくのは、そこに息づく一人ひとりの心なのです。
1-2. なぜ「住民の心」が街の未来を左右するのか
今、地域社会が直面している課題「少子高齢化、人口流出、地域経済の低迷」は、単なる設備や制度だけでは解決できない深い問題を抱えています。
どれほど利便性に優れた都市であっても、人びとが「この街に住みたい」「この街で生きていきたい」と感じなければ、やがて街は静かに力を失っていきます。逆に、小さな誇りや共感が積み重なっていけば、たとえ目立たない地方都市であっても、そこには温かな力強さが生まれるのです。
つまり、街の未来を支えるのは、施設やハードの充実ではなく、住民一人ひとりの想いの総体です。心が動くとき、街もまた生き生きと呼吸を始めるのです。
1-3. 本章のまとめ──街は「つくる」ものではなく「育む」もの
街は、誰かが一方的につくり上げるものではありません。行政が用意した基盤の上に、住民たちの暮らしと感情が重なり合うことで、はじめて「街らしさ」は芽生えていきます。
これからの街づくりに求められるのは、整備された施設や制度だけではありません。一人ひとりが持つ小さな想いを受け止め、共に育んでいくこと。そうした積み重ねの先に、真に愛される街が生まれていくのです。
行政と市民が互いに役割を理解し合い、手を取り合うとき、街は単なる場所ではなく、心が響き合う"生きた場"へと変わっていきます。
次は2章に続きます。