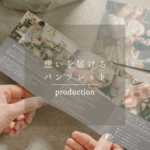消費型観光の限界と「共に生きる」という視点
かつての地域振興は、観光客を「呼び込む」ことに重きが置かれてきました。イベントや特産品、フォトスポットを中心に、「一度来てもらえれば成功」といった考え方が支配的でした。
しかし、SNS時代の現在、ただ一過性の訪問者を増やすだけでは、持続的な地域の力にはなりません。観光資源が"消費される対象"となることで、住民の生活や環境、文化との軋轢(あつれき)、つまり人の仲が悪くなり争いが生まれることもあります。
これから求められるのは、「観光客と地域住民」という分断された構図を超えた視点。つまり「共生のデザイン」です。訪れる人が一方的に受け取るのではなく、地域の営みに敬意を払い、対話し、共に地域の時間を過ごす関係性こそが、真の価値となります。
「共生」を実現する地域プロデュースの3つの視点

① 観光客ではなく“協力者”を増やす
地域に共感し、何度も訪れるリピーターや、地域課題の解決に関心をもつ外部人材は、単なる観光客以上の存在です。彼らを「協力者」として受け入れることで、地域の担い手不足や情報発信の課題が自然と補われていきます。
② 地域の「暮らし」と接続された体験設計
収穫体験や漁業体験だけでなく、「地元の人と一緒に夕飯をつくる」「学校や集落の活動に加わる」といった日常への参加が、訪れる側にとっても忘れがたい体験となります。観光は体験の“非日常”を求めますが、共生は“日常の尊さ”に光を当てます。
③ プロセスを共有する
地域のブランディングや空き家再生などのプロジェクトに、外部の人を途中段階から巻き込むことが重要です。完成されたものを「見せる」のではなく、課題や挑戦を共有することで、「一緒につくる喜び」が生まれます。
廃校から始まる共創の物語
西粟倉村・旧影石小学校の再生事例

岡山県にある西粟倉村(にしあわくらそん)は、平成に行われた市町村合併の流れには乗らず、自立する道を選んだ村です。
面積95%は森林であったこの村は、今やローカルベンチャーの先進地になっています。ここ15年で、多くの起業家やクリエイターら150人が新ビジネスの構想を携えて移住しそれぞれ成長を遂げました。
移住者の心を掴んだのは、合併をしない決断をしたときに村長が掲げた「地域を諦めない」という意思と、放置されていた森林に価値を取り戻し、村を創生させるという「百年の森林構想」だそうです。
どのような再編成を遂げていったのか、要約してお伝えしていきます。
1. 廃校を拠点に生まれたローカルベンチャーの群れ
- 1999年に閉校した旧影石小学校は、2008年に「西粟倉・森の学校」として再活用され、林業復興の拠点に。
- 現在は移住者やローカルベンチャー企業の拠点として活用されており、エーゼロ社もこの場所にオフィスを構える。
- 村内の起業家数は40社以上、移住者は150人を超え、人口の1割が移住者という驚異的な割合に。
2. 体育館で行う“森のうなぎ”養殖
- 廃校の体育館では、木材加工で出る端材を熱源にした温水循環で2万匹のうなぎを養殖。
- 飼料も環境負荷を考慮し調整。廃材、労働、エネルギーなどの地域資源を循環させるSDGs実践モデル。
- 「森のうなぎ」はふるさと納税の返礼品として販売され、寄付額は1億円以上に成長。
3. 村外に村人をつくる──アプリ村民票と情報発信
- Webメディア「Through Me」や「西粟倉アプリ村民票」により、村外ファンを獲得。
- 寄付金の用途やプロジェクト状況を透明化し、参加意識の高い“関係人口”を育てる仕組み。
- 「村外に住んでいても村人になれる」関係性をデジタルで可視化・構築している。
まとめ:「訪れる人」から「共にある人」へ
これからの地域プロデュースに求められるのは、「訪れる人を増やす」施策ではなく、「共に未来を描く人」をどう迎え入れ、関係を育んでいくかという視点です。
観光から共生へ──その変化は、地域の文化や風景だけでなく、そこにある「人」の営みを尊重する姿勢から始まります。持続可能な地域の力は、人と人の対話、そして「共にある」喜びの中に息づいています。